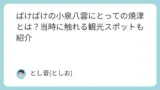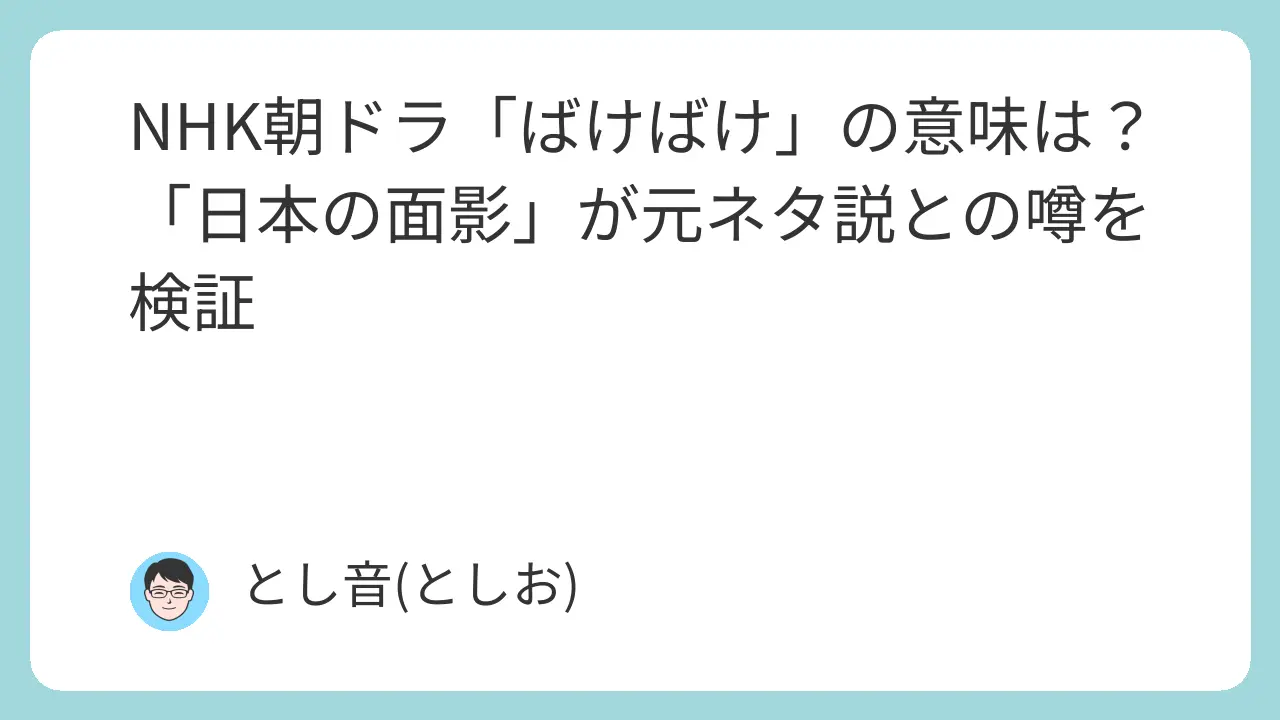NHK朝ドラ『ばけばけ』は朝ドラ史上で異例の「擬音の妖しげなタイトル」になっており、その不可思議さで注目を集めています。
今回は「ばけばけ」の言葉が持つ意味や、ドラマの背景から込められたタイトルの意味について紹介します。
また『ばけばけ』の放送を控え、インターネット上では、1984年に放送された山田太一脚本のNHKドラマ『日本の面影』が、その元ネタではないかという憶測が広まっています。
「日本の面影」との関係性は本当に存在するのかについて合わせて検証します。
是非最後までごらんください
「ばけばけ」の言葉の意味とドラマに込められた意味とは?
朝ドラ『ばけばけ』というタイトルには、“化ける/変化する”ことが主題に深く関係していて、ドラマのテーマを象徴する言葉として選ばれています。以下にその意味を整理します。
タイトル「ばけばけ」の意味
「ばけばけ」という言葉自体は日常ではあまり使われない言葉ですが、「化ける」「変わる」という意味の読みを中心に、比喩的にも直接的にも“変化”や“姿を変えること”を表す意味として使われています。
NHKでは、このドラマは「化ける物語」であると説明されています。
明治という激動の時代に、人々の暮らし・価値観が急速に変わっていく中で、主人公・トキの“うらめしい”と感じていた世界が、やがて「かけがえのない素晴らしいもの」に化けていく。
そういう“変化”の過程が描かれているから、タイトルが「ばけばけ」ということになります。
ばけばけのタイトルのドラマ背景は
ドラマの主人公は小泉セツで、彼女は没落武士の娘という立場で、時代の変化に翻弄されながらも強く生きていきます。
そのなかで物質的にも社会的にも価値観が移り変わり、自分や周囲の人々のあり方が「化けていく」姿が描かれます。
またセツは「怪談」が好きな少女という設定です。
怪談/妖怪/化け物など「化けるもの」の世界が、物語のモチーフとして入ってくるので、物理的な“化ける”だけでなく、
心や価値観・景色など見えないもの・感じるものが変わるという意味合いもあるようです。
NHKドラマ「日本の面影」が元ネタ説との噂について検証
NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の放送を控え、インターネット上では、1984年に放送された山田太一脚本のNHKドラマ『日本の面影』が、その元ネタではないかという憶測が広まっています。
どちらも小泉八雲と妻セツの物語を扱っているため、両作の類似点に着目した声が多く見受けられます
NHKドラマ「日本の面影」について
NHKドラマ『日本の面影』(1984年放送)と連続テレビ小説『ばけばけ』(2025年度後期放送)は、
どちらも明治時代に来日した作家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・小泉セツをモデルにした物語という共通点を持ちます。
| 日本の面影(1984年) | ばけばけ(2025年度後期) | |
|---|---|---|
| 放送種別 | ドラマスペシャル(4回シリーズ) | 連続テレビ小説 |
| 脚本 | 山田太一 | ふじきみつ彦 |
| 着眼点 | 小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の生涯を中心に描く。 | 小泉セツをモデルとしたヒロイン・松野トキの視点を中心に描く。 |
| 主人公 | ラフカディオ・ハーン(小泉八雲) | 松野トキ(小泉セツがモデル) |
| 「怪談」の扱い | 怪談話が劇中劇として盛り込まれる。 | 怪談話が好きなトキとヘブン(八雲がモデル)が心を通わせるきっかけとなる。 |
| 物語の舞台 | 主に明治時代の日本(特に松江)。 | 物語の始まりは松江。その後、トキの人生と共に熊本など各地に移り変わる |
「日本の面影」が元ネタ説について検証まとめ
NHKの制作発表によれば、『ばけばけ』は特定の原作を持たないフィクションであり、実在の人物をモデルに大胆に再構成された物語とされています。
したがって、『日本の面影』を直接的な「元ネタ」と断定することはできません。
この噂は、同じ題材を扱った過去作への関心の高さを示しているといえます。
この両作品の比較を通して、小泉八雲とセツの物語が時代を超えて人々の心を捉えてきたことがわかります。
まとめ
今回は「NHK朝ドラ「ばけばけ」の意味は?「日本の面影」が元ネタ説との噂を検証」のテーマでお届けしました。
『ばけばけ』という言葉の意味、“化ける/変化する”ことが主題に深く関係していて、ドラマのテーマを象徴する言葉として選ばれました。
明治という激動の時代に、人々の暮らし・価値観が急速に変わっていく中で、主人公・トキの“うらめしい”と感じていた世界が、やがて「かけがえのない素晴らしいもの」に化けていく。
そんな心や時代の移り変わりのなかで起こる人間模様がドラマの魅力ではないでしょうか。
最後までご覧下さりありがとうございました。
ばけばけ関連の記事はこちら↓